-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年1月 日 月 火 水 木 金 土 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
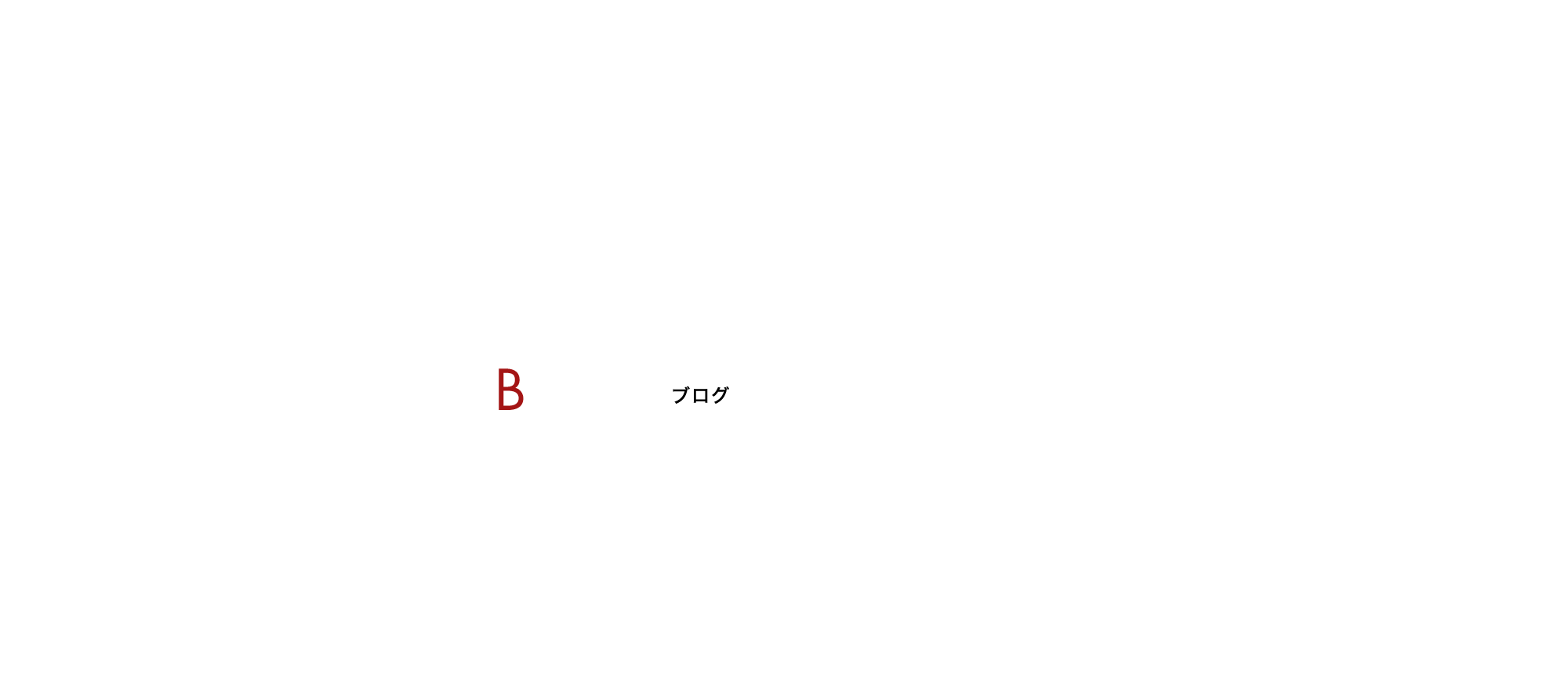
皆さんこんにちは!
株式会社NSK、更新担当の中西です。
防水の寿命は「水がたまらない形」と「確実な出口」で決まります。1mmの滞水が紫外線・熱・汚れを呼び、劣化を加速。今回は、勾配形成の設計・材料・施工管理と、改修・新築双方のドレン納まりを実装レベルでまとめます。
1. 勾配の基本思想—“水を走らせる道づくり”
• 目標勾配:理想は1/50(約2.0%)前後。最小でも1/100(約1.0%)は確保。広い屋上ほど余裕を持って設計します。
• 水は最短距離で落とす:長距離の面流れは滞水・汚れの温床。集水点(ドレン)を増やすか、水勾配を分割して距離を短く。
• “面→線→点”の流路設計:面(屋上・バルコニー)で走らせ、線(側溝・スリット)で集め、点(ドレン)で落とす。各階層の容量と断面を整合させて詰まらせない。
• 逆勾配の撲滅:不陸・沈下・補修の継ぎ当てで“谷”ができやすい。改修前の実測(レーザー・水糸)で谷地図を描くのが第一歩。
現場メモ:目視ではフラットに見えても逆勾配が潜んでいます。3mアルミ定規+レーザーで「高低差マップ」を作ると、勾配形成のモルタル/テーパー断熱の数量精度が劇的に上がります。
2. 勾配形成の3工法—長所・短所・使い分け
2-1. モルタルによる勾配調整(セメント系)
• 長所:自由形状・低コスト・局所補修が容易。薄塗り〜厚塗りまで対応。
• 短所:収縮クラック・含水の管理が難しい。乾燥期間が必要で工程が伸びがち。
• ポイント:
o 混和材で収縮低減・接着向上。
o 目地割り(誘発目地)で割れコントロール。
o 含水率が高いまま防水を被せない(膨れ・剥離リスク)。
2-2. テーパー断熱(保護断熱・外断熱)
• 長所:断熱性能向上と勾配形成を同時に実現。軽量で躯体負担が少ない。既存勾配のムラを吸収しやすい。
• 短所:材料コスト高め。立上り高さの確保やサッシ下端との干渉に注意。
• ポイント:
o 断熱の熱橋(笠木・金物・アンカー)を最小化。
o 端部段差の見切り金物で雨仕舞いを整える。
o 機械的固定か接着かは既存下地と風荷重で選定。
2-3. セルフレベリング(SL)+局所勾配補正
• 長所:平滑で美しい下地。膜厚管理がしやすい。微細な不陸補正に最適。
• 短所:勾配そのものは作りにくい。厚塗りはコスト増。含水・養生管理がシビア。
• ポイント:
o 先にモルタルやテーパー断熱で大勾配を作り、SLで仕上げの平滑を確保。
o 谷部の水溜まりスポットは別途“サドル・クリケット”で逃がす。
3. “谷”を消すディテール—サドル・クリケット
• サドル(Saddle):ドレン手前に盛り上げの丘を作り横からの水も集める。ドレン周りの逆流・滞水を防ぐ。
• クリケット(Cricket):障害物(塔屋・機器基礎)の背後に水返しの三角屋根を作り、左右へ水を振り分ける。
• 作り方:
o モルタル成形/テーパー断熱ブロック/ウレタン充填材の下地成形など。防水層と連続するよう納め、急勾配の段差は避ける。
4. ドレン計画—“出口設計”が命
4-1. ドレンの種類と選び方
• 改修用ドレン(差し込み式):既存ドレンの内側に差し込んで一体化。既存管の撤去不要で信頼性◎。
• 塩ビ・TPO・ゴム用ドレン:材料に合わせてフランジ一体。溶着/接着条件をメーカー手順に厳守。
• 横引き・縦引き:納まりと詰まりリスクで選定。横引きは逆勾配・堆積に注意。
• 緊急溢水(オーバーフロー):主要ドレンが詰まっても室内側に水が行かない高さ・位置に設ける(吐出面の意匠も配慮)。
4-2. 配置・数量の考え方
• 距離を短く:1つのドレンに向かう最長流路を短縮。分割して複数設置が基本。
• 端部からの距離:外壁や立上りから適正離隔(例:300〜500mm)を確保し、立上りの施工とメンテを容易に。
• 落ち葉・砂対策:ストレーナ(ごみ受け)+定期清掃。周辺が樹木豊富なら開口径大きめ・複数化で冗長性。
4-3. ドレン納まりの鉄則(改修・新築共通)
1. フランジの清掃・目荒し:油膜・ほこり・旧接着剤を確実に除去。
2. プライマー・溶着条件の厳守:温度・時間・圧着。試験片で溶着確認が理想。
3. 立上り〜ドレンの連続性:段差で水返しが切れないよう“面一”を意識。
4. 改修用ドレンの固定:コーキング頼みはNG。機械固定+止水材で多重化。
5. 緊急吐出の高さ設定:仕上レベルと内装しみ上がり高さを計算して、室外へ先出しの原則。
チェック:引渡し前に水張り試験(洪水試験)を計画。居住中は難しいケースも多いので、散水+レーザー水位で代替検証するなど、現場条件に合わせて“確からしさ”を積み上げます。⏱️
5. 立上り・端末・笠木の排水ディテール
• 立上り高さ:外部は原則200mm程度を目安(最低150mm)。サッシ下端が低い場合は水返し金物・溝型見切りで代替案。
• 笠木取り合い:ジョイント位置は水下に置かない。二重の水返しとシール二面接着で貫通止水。
• 出隅・入隅:コーナー部は補強メッシュや役物で応力集中を分散。
• 側溝(スリット):立上り際に浅い溝で線排水を作ると、面の滞水を減らせる。清掃性(幅・深さ)も設計要件。
6. 勾配・排水の“見える化”—計測と合否基準
• レーザーレベルで高低差を測定し、等高線図を簡易作成。改修前後を比較し逆勾配の撲滅を確認。
• 水たまり検査:散水停止60分後の滞水深さを記録。0〜数mmを目標、10mmを越える滞水は是正検討。
• ドレン流量:簡易的に満水→排水時間で流下能力を確認。ゴミ受け装着時の差も試す。
• 写真基準:広角→中景→寄り→ディテールの4点セットで誰が見ても分かる記録に。
7. 清掃計画も“設計”の一部
• 落ち葉期の前倒し清掃:秋だけでなく、春の花がら・虫の大量発生時期も詰まりやすい。
• 清掃動線:はしご・点検口・親綱アンカーの配置はメンテしやすい設計に直結。
• オーバーフロー点検:実際に水を流して外壁の汚れ・吐出位置・音を確認。クレーム予防に効果絶大。
8. 材料別の相性—ウレタン/シート/アスファルトの勾配観点
• ウレタン塗膜:平滑性が命。ピンホール対策に下地の気泡止め・プライマーの選定・通気緩衝工法+脱気筒で含水とガスを逃がす。
• シート防水:皺・ブリッジが勾配と相性悪化。曲率の大きい谷部は部分的に塗膜で納めるハイブリッドも選択肢。
• アスファルト:長寿命だが熱工法は火気・臭気対策が必須。大型屋上で計画的な勾配形成と相性良。
9. ケーススタディ:大型屋上の慢性的滞水を解消
状況:築25年RC造、屋上800㎡。既存は塩ビシート。中央機器基礎の背後に常時10〜15mm滞水。
診断:塔屋・基礎背面に谷地形。ドレン3基で流路が長い。オーバーフローは外壁の意匠上、吐出が外壁を汚してクレーム化。
対策: 1. テーパー断熱で“面の大勾配”を再構築(目標1/60)。 2. 基礎背面にクリケットを新設し、左右へ分流。 3. ドレンを3→5基に増設。各ドレン前にサドルを設置。 4. オーバーフローの吐出先を庇上に変更、縦樋で地上へ。
結果:散水停止60分後の滞水ゼロ。夏季表面温度が最大6℃低下し、材料負荷も軽減。清掃頻度は年2回→年1回へ。
10. 失敗あるあると未然防止 ⚠️
• ドレンだけ新品:周辺の逆勾配・谷がそのままで効果半減。→ 勾配形成とセットで設計。
• サッシ下端が低すぎ:立上り高さが取れずに水返し不足。→ 金物ディテール+部分段差で“見えない水返し”。
• 機器脚の“島”:四隅で水が回り込み滞水。→ 四辺の面取り+クリケットで水を逃がす。
• 清掃前提の過信:現実は清掃頻度が落ちる。→ 冗長化(複数ドレン)+大開口ストレーナで安全側へ。
11. 現場5分チェックリスト ✅
☐ レーザーで高低差測定→逆勾配地図の作成
☐ 目標勾配(1/50〜1/100)と勾配形成工法の確定
☐ サドル・クリケットの位置と寸法の合意
☐ ドレンの数量・位置・緊急吐出の高さ設定
☐ 立上り高さ(外部200mm目安)とサッシ干渉の解消案
☐ 材料別の納まり(ウレタン/シート/アスファルト)図
☐ 水張りor散水+レーザー水位で検証手順を事前共有
☐ 清掃・点検動線と安全設備(親綱・アンカー)の位置
12. まとめ—“走らせ・集め・落とす”を数値で証明
勾配は感覚ではなく数値と図で作る時代。レーザー・テーパー断熱・サドル/クリケット・改修用ドレンを組み合わせ、短い流路・冗長な出口・高い立上りで漏水リスクを根本から削る。最後は、滞水深・排水時間・写真で“水が動く建物”を証明しましょう。
次回予告:「第4回 下地補修(ひび割れ・爆裂・脆弱層の除去)」—防水は下地が命。爆裂の見極め、Uカット・樹脂注入、断面修復材の選定、可使時間・養生・打継ぎの勘所まで総ざらいします。
株式会社NSKでは一緒に働く仲間を募集しています♪
お問い合わせは↓をタップ♪