-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
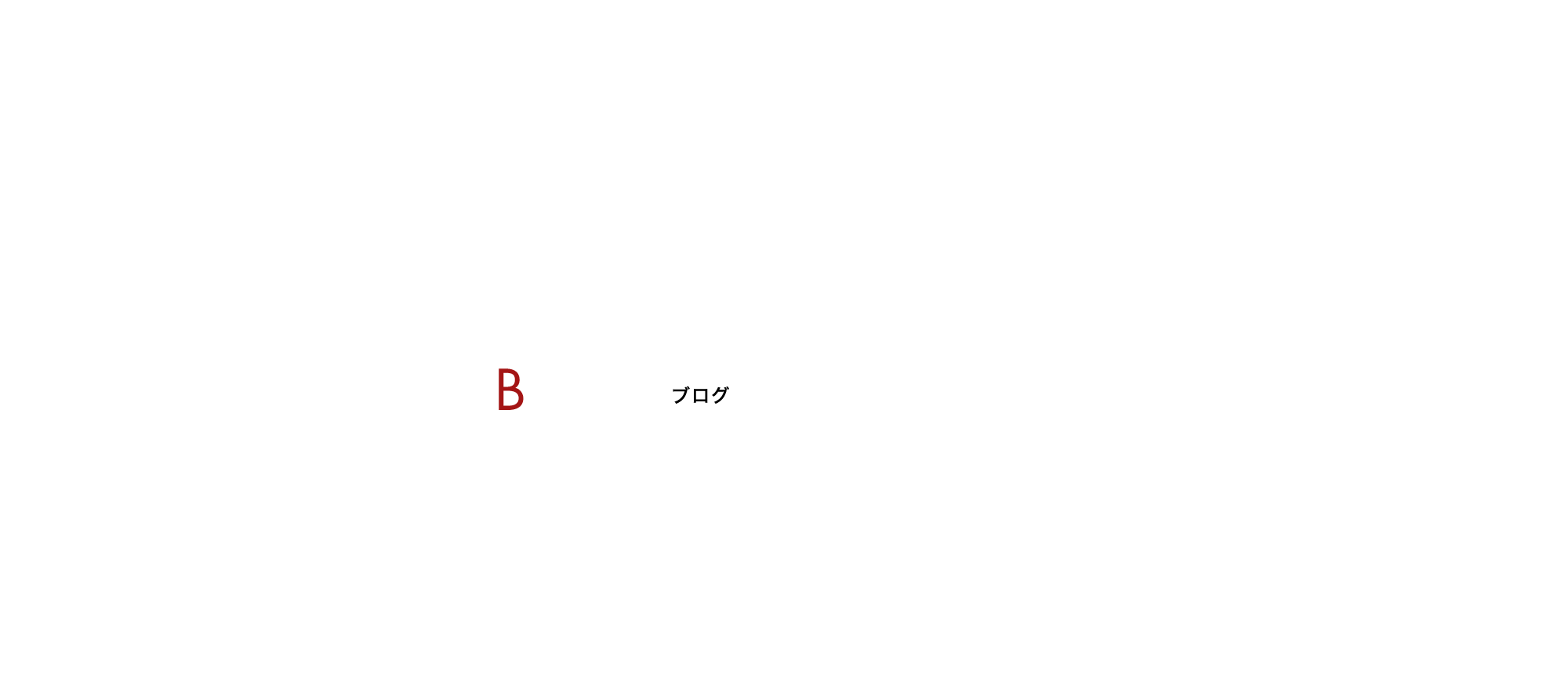
皆さんこんにちは!
株式会社NSK、更新担当の中西です。
ウレタン塗膜防水は「連続した無目地の膜」で複雑ディテールにも追随できる万能選手。いっぽうで下地の含水・気泡・気象条件に敏感で、“やり方の型”が寿命を左右します。本回は通気緩衝工法と密着工法の仕組み・選定・標準工程を、現場でそのまま使えるレベルで整理します。
1. 用語と基本構成
• 密着工法:プライマーの上にウレタン主材を直接積層し、下地と一体化。軽歩行〜ベランダ・庇などに多用。
• 通気緩衝工法:下地上に通気層(通気シート/通気マット)を敷設→その上にウレタン。脱気筒で水蒸気や下地ガスを逃がし、膨れを抑制。屋上や含水下地の改修向き。
• トップコート:紫外線劣化を抑え、汚れ・擦れを低減する保護層(ウレタンやフッ素系など)。
要点: – 含水・ガスが心配→通気緩衝。 – 軽量・低コスト・工期短縮→密着(ただし下地乾燥・付着が前提)。
2. 選定基準(現場判断の軸)
• 下地含水:高い→通気緩衝+脱気。低い→密着可。
• 動き・振動:大→通気緩衝(応力分散)、小→密着。
• ディテール複雑:どちらも可だが、入隅R・端末補強を厚めに。
• 臭気・騒音制限:水性プライマー・低臭タイプを選択、熱工法回避。
• 工程制約:雨期は通気×脱気でリスク分散。晴天続きは密着がスムーズ。
3. 必要資機材チェックリスト
• 計測:温湿度計・表面温度計・露点表・含水計・WFTゲージ(湿膜厚)・針式膜厚計(硬化後)
• 施工:撹拌機・計量器・スキージー・鏝・ローラー・メッシュ/不織布・改修用ドレン・脱気筒・マスカー・養生材
• 安全:ハーネス・親綱アンカー・火気厳禁標識・保護具(手袋・マスク・ゴーグル)
4. 標準工程フロー(密着工法)
1. 清掃・下地調整:脆弱層除去・不陸補修・入隅R出し(10〜20mm)。
2. プライマー:下地別に選定(第5回参照)。WFTで塗り逃しゼロを確認。
3. 端部・立上り補強:不織布・メッシュで応力分散。入隅・出隅は先行二度塗り。
4. 主材1層目:規定量を均一膜厚で。ピンホール出やすいので、ローラー仕上げで気泡つぶし。
5. 中間検査:気泡・ピンホール・膜厚・段差の是正。
6. 主材2層目:所定膜厚に到達するよう総量管理。端末・立上りを厚めに。
7. トップコート:色むら・塗り継ぎラインを消し、歩行・汚染に備える。
⏱️ 再塗り時間(目安):気温20℃で数時間〜翌日。露点差3℃以上・湿度85%以下を目安に。※実材の仕様書優先。
5. 標準工程フロー(通気緩衝工法)
1. 清掃・下地調整:谷・逆勾配を補修(第3回)。
2. プライマー:通気用(半湿潤面可)を選定。吸い込みが強い箇所は二度塗り。
3. 通気シート/マット敷設:重ねは規定幅、ジョイントはテープ等で通気連続性を確保。
4. 端末処理:端部は通気止め(シールや樹脂)で外周からの水分侵入をカット。
5. 脱気筒:高所側・広面中央に配置。屋上規模に応じ複数設置(例:10〜15mピッチ)。
6. 補強:立上り・入隅・貫通部・改修用ドレン周りを先行補強。
7. 主材1・2層:ジョイント段差を消しつつ、通気層に均一に被覆。
8. トップコート:色・艶の均一化、耐候性付与。
コツ:通気マットの断面端部は“毛細管で吸い上げない”よう、端部封止を徹底。脱気筒は日射で温まる位置が効果的。
6. 膜厚・使用量の目安(あくまで一般例)
• ベランダ・庇(密着):総膜厚1.5〜2.0mm相当。
• 屋上(通気緩衝):総膜厚2.0〜3.0mm相当。
• WFT→DFT:溶剤・反応収縮で乾燥後は薄くなる前提。総量(kg/㎡)で管理するのが確実。
• 測定:
o 施工中:WFTゲージで湿膜を随時チェック。
o 施工後:試験片・端部の針式/磁気式で参考値を取る(※破壊計測は位置合意)。
7. 気象・環境管理
• 温度:下地・材料・気温が5〜35℃の範囲(例)。高温時は可使時間短縮。低温時は硬化遅延。
• 湿度:85%以下を目安。霧・露・結露は施工中止。
• 露点差:表面温度−露点≧3℃を確保。
• 風:乾燥促進するが、砂塵混入に注意。風下に養生カーテン。
• 雨:降雨予報なら工程を切る(端末まで完結)。
8. 端末・立上り・ディテール
• 入隅R:10〜20mmで塗膜破断を防止。R成形→先行塗り→補強布→本体。
• 出隅補強:コーナーパッチで応力集中を回避。
• 改修用ドレン:差し込み+機械固定+止水材で多重化。通気層と面一に。
• 笠木・金物:水返し金物で毛細管上がりを遮断。シールは二面接着で。
• 貫通部:スリーブ+止水リング+可とうシール→上から塗膜包みで再発防止。
9. 品質管理(ITP)—“見える化”の要点
• 材料管理:ロット・残量・使用数量(kg/㎡)を日報で記録。
• 写真:
o 施工面:広角→中景→寄り→ディテールの4点。
o 検査面:WFT測定・膜厚ゲージの数値が写る写真。
• 試験:
o テープテスト(付着)
o 目視(ピンホール・泡・段差)
o 必要に応じプルオフ試験(引張付着)。
10. よくある不具合と予防・是正 ⚠️
• ピンホール:下地気泡・吸い込み差。→ 気泡止めプライマー・ローラー潰し・薄塗り→重ねで回避。発生部は研磨→再塗。
• 膨れ:含水閉じ込め・ガス膨張。→ 通気緩衝+脱気、含水ログでGo/No-Go判断。生じた膨れは切開→乾燥→補修。
• 白化・艶引け:露点未管理・霧雨。→ 天気読み・時間帯調整。白化部は研磨→再塗。
• ムラ・流れ:過剰塗布・傾斜。→ 規定量・勾配側は多層薄塗り。
• 付着不良:脱脂不足・粉塵残り。→ 清掃徹底・プライマー再施工。
11. 安全・臭気・近隣配慮
• 臭気クレーム:低臭材・夜間避け・風下への事前掲示。
• 可燃性溶剤:火気厳禁・換気・静電気対策。
• 転落・滑落:親綱・先行安全帯・通行分離。
• 騒音:撹拌・研磨は時間帯配慮。
12. ケーススタディ
12-1. RC屋上(含水高め)→通気緩衝
• 背景:雨上がりの滞水多く、過去に膨れ。
• 対策:通気マット+脱気筒増設。端部封止徹底。主材2層で総膜厚約2.5mm相当。
• 結果:夏期の表面温上昇時も膨れゼロ。引渡し前の散水試験で圧抜け良好。
12-2. ベランダ(乾燥良好)→密着
• 背景:庇付きで乾きやすい。ディテール複雑。
• 対策:密着で端末補強厚め。立上りは2回増し塗り。
• 結果:ピンホールなし、鏡面に近い平滑で美観◎。
13. 現場5分チェックリスト ✅
☐ 密着/通気の選定根拠(含水・動き・工程)
☐ プライマー種類・塗布量・WFT写真
☐ 端末・入隅・立上りの補強布配置
☐ 総量(kg/㎡)と所定総膜厚の到達見込み
☐ 通気層の端部封止と脱気筒位置
☐ 気象(温度・湿度・露点差3℃)のログ
☐ 中間検査の是正事項の完了
☐ トップコートの色・艶の均一性
14. まとめ—“型を守れば裏切らない”
ウレタン塗膜は下地と気象の管理さえできれば、どんな形にも“連続膜”で応えてくれる頼れる工法。通気緩衝で含水・ガスを受け流し、密着で軽快に仕上げる。膜厚=寿命と心得て、総量・WFT・再塗時間・露点差を数字で管理しましょう。
株式会社NSKでは一緒に働く仲間を募集しています♪
お問い合わせは↓をタップ♪
皆さんこんにちは!
株式会社NSK、更新担当の中西です。
プライマーは“魔法の糊”ではありません。 下地と主防水の“通訳”であり、付着・密着・バリア・封止・濡れ性の最適化という“機能設計”そのもの。もう一方の主役は含水率。水を抱えた下地に膜を被せれば、膨れ・白化・剥離は必然です。本回は、下地別のプライマー選定、塗布量・オープンタイム、露点・含水の管理を数値でマネジメントする方法を解説します。
1. プライマーの役割を5分で整理
• 付着向上(アンカー効果):微細孔へ浸透→機械的かみ込みを作る。
• 表面改質(濡れ性UP):表面エネルギーを上げ、主材が“馴染む”状態に。
• バリア・封止:アルカリ・可塑剤・残留塩分・粉塵を遮断し界面トラブルを抑制。
• 含水・気泡対策:ポリマーで気泡止め、通気緩衝工法では水蒸気逃げ道を確保。
• 接着界面の均質化:下地ムラ(吸い込み差)を均すことで膜厚の安定につなげる。
2. 下地別:プライマー選定の実務
2-1. コンクリート/モルタル(RC・押え)
• 課題:アルカリ・レイタンス・含水・吸い込み差。
• 指針:
o エポキシ系(溶剤 or 水性)で高付着・封止。ピンホール多い場合は下地調整材併用。
o 含水が高め→湿潤面対応型や通気緩衝用プライマーを選ぶ。
o 仕上げがウレタン塗膜の場合は同系統の相性を優先。
2-2. ALC・軽量気泡コンクリート
• 課題:吸水率が高く含水変動が大きい。
• 指針:
o 浸透シーラー(アクリル/シラン系)で吸い込みを均質化。
o 水分を抱えやすいので晴天連続日を確保。端部は可とう型シールで動きに追随。️
2-3. 金属(亜鉛メッキ・ステンレス・アルミ)
• 課題:表面エネルギー低く、酸化膜や油分が付着。
• 指針:
o 脱脂(アルカリ洗浄→水洗→乾燥)→目荒し(#120〜240)→金属用プライマー(変性エポ・変性ウレ)。
o 亜鉛メッキは白錆除去を徹底。端部は二次防水の重ねで金物頼みを避ける。
2-4. 木質・合板・ケイカル
• 課題:吸い込みが強く、寸法変化が大きい。
• 指針:
o 浸透型シーラー+可とう型プライマーで動きに耐える界面を形成。
o 端面(木口)は多め塗りで吸い込み差を消す。
2-5. 旧防水層(ウレタン・FRP・塩ビ・TPO・ゴム)
• 課題:可塑剤移行・表面劣化・相溶性。
• 指針:
o 同系統プライマーが基本。塩ビ→可塑剤ブロック型、TPO→専用接着、FRP→アセトン拭き+サンディング→樹脂プライマー。
o 露出ゴムは研磨+専用プライマーで界面を作る。
2-6. タイル・石材
• 課題:吸水ムラ・表面光沢・目地の“線”が水みちに。
• 指針:
o サンディング→アルカリ洗浄→水洗→乾燥。
o エポキシ系シーラーで封止し、塗膜系やシートのブリッジを作る。
3. 含水率・露点の管理—Go/No-Goを数値で
• 含水率の目安(相対比較の実務例):
o コンクリート/モルタル:表層5%以下相当を目標(機器ごとの換算に注意)。
o ALC:乾燥傾向が続く状態で施工(数値は機器差が大)。
o 木質:12〜15%以下相当が目安。
• 測り方:
o 非破壊式で面の分布→ピン式で要所の深部傾向を見る“二段構え”。
o 同一位置を時系列で記録し、下降トレンドを確認。
• 露点管理:
o 表面温度と気温・湿度から露点差3℃以上を確保(結露・白化防止)。
o 早朝・夕方の結露時間帯は避ける。温湿度計は常時見える位置に。
• 天気の読み:
o 雨上がり直後/北面日陰は乾きが遅い。
o 風は乾燥を助けるが、ゴミ付着・塵巻き込みに注意。
4. 塗布量・オープンタイム・膜厚管理
• 塗布量:メーカー規定○○g/㎡を厳守。多過ぎ=乾かない/少な過ぎ=付着不足。
• WFT(湿膜厚)ゲージで塗り切りを確認。均一に塗り逃しゼロ。
• オープンタイム:早過ぎ→濡れ性不足、遅過ぎ→再付着不良。指触乾燥〜半硬化の間に主材を被せる設計を。
• 二度塗り:吸い込みが強い下地はシーラー→プライマーの二段も選択肢。※溶剤攻撃に注意。
• 攪拌・可使時間:
o 秤量・撹拌時間をタイマーで管理。
o インダクションタイム(反応時間)が必要な二液型は待ち時間を守る。⏳
5. 施工手順(標準フロー)
1. 清掃・脱脂:粉塵・油膜・離型剤を除去。
2. 含水・温湿度・露点差の記録。
3. 試験塗り:1㎡程度で乾燥と付着の挙動を確認。
4. 本塗布:端部・入隅・立上りは先行塗り+面塗り。
5. 乾燥管理:人・埃の侵入防止、鳥糞・虫の混入対策。
6. 合否判定:指触→テープテスト→必要に応じプルオフ試験。
6. 互換性・化学的トラブルの未然防止 ⚠️
• 可塑剤移行(塩ビ系):バリア型プライマーで遮断、または同系シート溶着に切替。
• 溶剤攻撃:旧塗膜を軟化・溶解させない配合を選定。事前に隅でパッチテスト。
• アルカリ焼け:モルタル新設はアルカリ強い→封止型+十分な養生。
• 紫外線・熱:夏場の黒色下地は表面温60℃超も。朝夕へシフト。
7. 季節別の運用術
• 梅雨〜夏:
o 短時間豪雨→急乾→結露の気象ローテに注意。
o 風通しを活かしつつ、虫・綿毛混入対策。
• 秋:
o 乾燥しやすいが落ち葉で汚染。清掃頻度UP。
• 冬:
o 露点差が小さく結露しやすい。日当たりの良い時間帯に限定。
o 加温は火気・一酸化炭素・延焼対策を最優先。
8. トラブル事例とリカバリー
• 白化(ブラッシング):湿潤・露点未管理。→ 再研磨→再プライム。
• 膨れ:含水閉じ込め・ガス膨張。→ 脱気筒増設/通気層見直し。
• ベタつき:過剰塗布・溶剤残り。→ 希釈・塗布量見直し、乾燥促進。
• ピンホール:下地気泡・吸い込み差。→ 気泡止めプライマー/下地調整材追加。
• 付着不良:脱脂不足・可塑剤移行。→ 化学洗浄→バリア型に切替。
9. 現場5分チェックリスト ✅
☐ 清掃・脱脂は手で触って滑らないレベルまで
☐ 含水・温湿度・表面温・露点差3℃以上
☐ プライマーの種類・希釈・塗布量・WFTを確認
☐ オープンタイムの目安と貼付け/塗り重ね時間
☐ 端部・入隅・立上りの先行処理
☐ パッチテストの結果写真を残す
☐ 通気緩衝の場合脱気計画と配置
☐ 施工後の手触り・テープテストで即時合否
10. ケーススタディ
10-1. RC屋上×通気緩衝ウレタン
• 課題:梅雨明け直後で含水高め。過去に膨れ発生。
• 対応:通気緩衝用プライマー+脱気筒ピッチ短縮。WFTゲージで湿膜80μm(例)管理。朝夕施工。
• 結果:夏期の表面温上昇時も膨れなし。引渡し前の散水→圧抜け良好で安定。
10-2. 既存FRPベランダの再防水
• 課題:表面チョーキング・ヘアクラック。溶剤攻撃の懸念。
• 対応:#120サンディング→アセトン拭き→樹脂プライマー。端部はガラスマット増張り。
• 結果:引張付着試験OK。塗膜系仕上げで鏡面に近い平滑を実現。✨
10-3. 露出塩ビシートの上に塗膜
• 課題:可塑剤移行でベタつき・汚染。
• 対応:可塑剤バリア型プライマー+試験塗りで相性確認。オープンタイム短め運用。
• 結果:歩行荷重下でも汚染なし・剥離なし。
10-4. 金属笠木の局所止水
• 課題:ジョイント部からの浸入。油膜と白錆。
• 対応:脱脂→目荒し→金属用プライマー。二面接着でシール。上から端末金物で二重化。
• 結果:台風時も漏水ゼロ。
11. まとめ—“プライマー×含水”を制す者が寿命を伸ばす
プライマーは下地と主材をつなぐ設計そのもの。含水・露点・塗布量・時間という4つの数値を揃え、下地別の相性に沿って試験塗り→本番の順で確実に。これだけで膨れ・白化・剥離の8割は防げます。明日から、WFTゲージ・温湿度計・含水計を“必携三種の神器”にしましょう。
株式会社NSKでは一緒に働く仲間を募集しています♪
お問い合わせは↓をタップ♪
皆さんこんにちは!
株式会社NSK、更新担当の中西です。
防水は“下地が9割”。下地が整っていなければ、どれほど高性能な防水材でも本来の寿命を発揮できません。今回は、RC・モルタル・ALC・金属デッキ・木下地など下地別の劣化形態を整理し、補修材の選定・手順・検査までを実務の視点で体系化します。
1. 原状把握—どの劣化が“水みち”に直結するか
• 構造クラック(貫通・動きあり):温度応力・乾燥収縮・地震で発生。動き追随性のある充填/止水が必要。
• 表層クラック(ヘアライン):主に乾燥収縮。塗膜で橋渡し可能だが、連続性と深さを確認。
• 爆裂(鉄筋腐食):錆膨張でかぶりが剥離。構造耐久性と再劣化の観点から最優先で補修。
• 脆弱層(レイタンス・脆弱モルタル):付着不良の温床。機械的除去が基本。
• 欠損・ジャンカ・蜂の巣:空隙が貯水室に。断面修復で空隙をゼロに。
• 動荷重・振動の影響:廊下・屋上機器基礎周りは疲労クラックに注意。
TIP:劣化の“地図”を作る。A3平面に赤=爆裂/橙=構造Cr/黄=表層Cr/青=脆弱層で色分けし、写真番号と連携。補修数量の見積精度と現場指示の透明性が上がります。
2. ひび割れの分類と対処法 ✍️
• 幅0.2mm未満(ヘアライン):表面含浸(シラン・シロキサン系)や微弾性塗材で水の浸透を抑制。
• 幅0.2〜0.5mm(微細〜中):Uカット+シーリング、または低粘度エポキシ注入で連続止水。動きが見込まれる部位は可とう型を選択。
• 幅0.5mm以上(開口):Uカット/Vカットで健全部まで切り、プライマー→バックアップ材→シール。構造的な連続性が必要な箇所はエポキシ樹脂注入で“接着”を先に。
• 貫通クラック:室内側のシミ・滞水が伴う場合は両面処理(外部:止水、内部:化粧補修)を計画。
Uカットの基本手順(RC・モルタル)
1. 墨出し→カッターでU字に切り込み(深さ10〜15mm目安)。
2. ダスト除去→エアブロー+吸塵。必要に応じアセトン拭き。
3. プライマー塗布→規定量を守りオープンタイム厳守。
4. バックアップ材→二面接着を確保。底付けは厳禁。
5. シーリング充填→ヘラで面一に成形。端部のピンホール注意。
6. 養生→表面皮膜形成まで防塵・防水管理。⏳
3. 爆裂補修—“原因=鉄筋腐食”にアプローチ
• 診断:中空音・鉄筋露出・錆汁。かぶり厚を実測し、腐食範囲を把握。
• はつり:周囲を健全部+10〜20mmまで機械はつり。刃先の振動による二次クラックに注意。
• 鉄筋処理:ワイヤブラシ・サンダーで白錆近くまでケレン。防錆材(無機ジンク・ポリマーセメント系)で被覆。
• 断面修復:
o 急結厳禁:急ぐと収縮割れ・界面剥離のリスク。
o 素材選定:ポリマーセメント系(汎用)/エポキシモルタル(高付着)/繊維補強(厚肉)。
o 打継ぎ処理:親水化→プレウェット→プライマー/ボンド施工。
• 仕上げ:周辺との平滑な面一を確保し、角欠けは面取りで応力分散。
✅ 検査ポイント: – [ ] はつり範囲に錆残りがないか(鏡・ライト併用)。 – [ ] 鉄筋背面まで周到にケレンできたか。 – [ ] 断面修復材の充填密度(空洞・豆板なし)。 – [ ] 24h後の表面ひび割れの有無。
4. 脆弱層の除去—“付着を邪魔するもの”を消す
• レイタンス・白華・チョーキング:ワイヤーブラシ・ディスクサンダーで除去。粉塵を残さない。
• 旧防水・塗膜の剥離部:全面撤去 or 健全部まで切り戻し。境界は段差見切りで勾配を崩さない。
• 油分・離型剤:中性洗剤・アルカリ洗浄→高圧水洗→完全乾燥。油分はプライマーの最凶の敵。
5. 断面修復材・樹脂の選び方
• ポリマーセメントモルタル:付着・耐水性バランス良。大面積の基本形。
• エポキシモルタル:高付着・低収縮。端末・角部・点荷重部に◎。ただし熱環境に注意。
• 無収縮グラウト:機器基礎やボルト周りの充填に。
• 可とう型シーリング:動きがある取り合い・クラック追随が必要な箇所に。
• ウレタン樹脂注入:止水重視。含水部でも反応するタイプを選択。
• エポキシ樹脂注入:接着・一体化が目的。乾燥条件が必要。
選定の軸:動く/動かない、乾いている/濡れている、点荷重/面荷重、紫外線の有無、厚み、工期。
6. 金物・貫通部・アンカー跡の止水
• アンカー孔:穿孔→清掃→プライマー→止水材→機械固定の順。コーキング単独はNG。
• 貫通配管:スリーブ周りは止水リング+可とうシール。温度変化で動くため追随性を優先。
• 笠木ビス:ビス頭に頼らず、下地木口の防水端末を強化。差し込み金物で二重化。
7. 含水管理と乾燥—“急がば回れ”の核心
• 含水の悪影響:膨れ・剥離・白化・泡噛み。通気緩衝工法でも限界はある。
• 測定:ピン式・非破壊式の相対値で経時変化を追う。同一機器・同一条件で比較。
• 乾燥戦略:
o 風通し・除湿・送風・加温(安全管理)。
o 脱気筒の計画的配置。
o 雨期は工程バッファを見込む。⏱️
8. 下地平滑化—膜厚・溶着を左右する仕上げ
• 不陸調整:防水層が均一厚で乗るよう、3m定規で±3mm以内(目安)に。
• 入隅・出隅のR:10〜20mmの面取り/R出しで塗膜破断を防止。
• 目地処理:シート重ね代/塗膜のブリッジに影響。段差を消す。
9. 品質管理(ITP)—数値と写真で“見える化”
• 記録:
o ステップごとにBefore/After。
o 材料のロット・使用量。
o 気象(温湿度・風速)。
o 養生時間のタイムスタンプ。
• 合否:
o 目視:欠損・段差・ひび。
o たたき:中空音なし。
o 付着:引張付着試験(必要に応じ)で0.7N/mm²以上(例)。
10. ケーススタディ
10-1. バルコニー床の微細クラック網状
• 状況:築15年、モルタル押えにヘアライン網状。雨後にシミ。
• 対策:
1) 含水確認→表面含浸(シラン系)で吸水抑制。
2) 入隅はUカット+可とう型で動きに追随。
3) 上から通気緩衝ウレタンで主防水。
• 結果:降雨後の滞水ゼロ、シミ解消。
10-2. 屋上の爆裂多数(鉄筋露出)
• 状況:築30年RC、屋上押えコンクリートに爆裂30箇所。
• 対策:
1) はつり+ケレン+防錆を徹底。
2) 繊維補強モルタルで断面修復。
3) 仕上げは機械的固定シートで振動の影響を低減。
• 結果:一年点検で再爆裂なし。表面温度低下で劣化速度も緩和。
11. 失敗あるあると回避策 ⚠️
• はつり甘く錆残り→再爆裂。→白錆レベルまで徹底ケレン。
• Uカット底付け→三面接着で早期破断。→バックアップ材必須。
• 粉塵残り→付着不良。→吸塵+脱脂をルーチン化。
• 乾燥不足→膨れ。→含水ログでGo/No-Go判断。
• 材料の混練ミス→硬化不良。→秤量と撹拌時間を数値管理。⏱️
12. 現場5分チェックリスト ✅
☐ 劣化地図の作成(色分け・写真連番)
☐ Uカット/注入の適用範囲と材料確定
☐ 爆裂部のはつり境界と防錆材の種類
☐ 断面修復材の配合・可使時間・打継ぎ処理
☐ 脆弱層・油分・粉塵の完全除去
☐ 入隅R・不陸±3mm以内の平滑化
☐ 含水・温湿度・養生ログの準備
☐ 合否(付着試験/中空音/外観)と写真基準
13. まとめ—“防水は化粧、下地は骨格”
美しい塗膜やシートの裏側で、下地が静かに寿命を決めています。クラック・爆裂・脆弱層を原因別に処方し、乾燥・付着・平滑を数値で満たす。ここを丁寧に積み上げれば、防水の寿命は数年以上伸ばせます。今日から下地に時間を投資しましょう。
次回予告:「第5回 プライマーと含水率管理」—“プライマーは魔法の糊ではない”。素材別の選定・希釈・塗布量・オープンタイム、含水の見極めとGo/No-Go判断、失敗事例まで深掘りします。
株式会社NSKでは一緒に働く仲間を募集しています♪
お問い合わせは↓をタップ♪
皆さんこんにちは!
株式会社NSK、更新担当の中西です。
防水の寿命は「水がたまらない形」と「確実な出口」で決まります。1mmの滞水が紫外線・熱・汚れを呼び、劣化を加速。今回は、勾配形成の設計・材料・施工管理と、改修・新築双方のドレン納まりを実装レベルでまとめます。
1. 勾配の基本思想—“水を走らせる道づくり”
• 目標勾配:理想は1/50(約2.0%)前後。最小でも1/100(約1.0%)は確保。広い屋上ほど余裕を持って設計します。
• 水は最短距離で落とす:長距離の面流れは滞水・汚れの温床。集水点(ドレン)を増やすか、水勾配を分割して距離を短く。
• “面→線→点”の流路設計:面(屋上・バルコニー)で走らせ、線(側溝・スリット)で集め、点(ドレン)で落とす。各階層の容量と断面を整合させて詰まらせない。
• 逆勾配の撲滅:不陸・沈下・補修の継ぎ当てで“谷”ができやすい。改修前の実測(レーザー・水糸)で谷地図を描くのが第一歩。
現場メモ:目視ではフラットに見えても逆勾配が潜んでいます。3mアルミ定規+レーザーで「高低差マップ」を作ると、勾配形成のモルタル/テーパー断熱の数量精度が劇的に上がります。
2. 勾配形成の3工法—長所・短所・使い分け
2-1. モルタルによる勾配調整(セメント系)
• 長所:自由形状・低コスト・局所補修が容易。薄塗り〜厚塗りまで対応。
• 短所:収縮クラック・含水の管理が難しい。乾燥期間が必要で工程が伸びがち。
• ポイント:
o 混和材で収縮低減・接着向上。
o 目地割り(誘発目地)で割れコントロール。
o 含水率が高いまま防水を被せない(膨れ・剥離リスク)。
2-2. テーパー断熱(保護断熱・外断熱)
• 長所:断熱性能向上と勾配形成を同時に実現。軽量で躯体負担が少ない。既存勾配のムラを吸収しやすい。
• 短所:材料コスト高め。立上り高さの確保やサッシ下端との干渉に注意。
• ポイント:
o 断熱の熱橋(笠木・金物・アンカー)を最小化。
o 端部段差の見切り金物で雨仕舞いを整える。
o 機械的固定か接着かは既存下地と風荷重で選定。
2-3. セルフレベリング(SL)+局所勾配補正
• 長所:平滑で美しい下地。膜厚管理がしやすい。微細な不陸補正に最適。
• 短所:勾配そのものは作りにくい。厚塗りはコスト増。含水・養生管理がシビア。
• ポイント:
o 先にモルタルやテーパー断熱で大勾配を作り、SLで仕上げの平滑を確保。
o 谷部の水溜まりスポットは別途“サドル・クリケット”で逃がす。
3. “谷”を消すディテール—サドル・クリケット
• サドル(Saddle):ドレン手前に盛り上げの丘を作り横からの水も集める。ドレン周りの逆流・滞水を防ぐ。
• クリケット(Cricket):障害物(塔屋・機器基礎)の背後に水返しの三角屋根を作り、左右へ水を振り分ける。
• 作り方:
o モルタル成形/テーパー断熱ブロック/ウレタン充填材の下地成形など。防水層と連続するよう納め、急勾配の段差は避ける。
4. ドレン計画—“出口設計”が命
4-1. ドレンの種類と選び方
• 改修用ドレン(差し込み式):既存ドレンの内側に差し込んで一体化。既存管の撤去不要で信頼性◎。
• 塩ビ・TPO・ゴム用ドレン:材料に合わせてフランジ一体。溶着/接着条件をメーカー手順に厳守。
• 横引き・縦引き:納まりと詰まりリスクで選定。横引きは逆勾配・堆積に注意。
• 緊急溢水(オーバーフロー):主要ドレンが詰まっても室内側に水が行かない高さ・位置に設ける(吐出面の意匠も配慮)。
4-2. 配置・数量の考え方
• 距離を短く:1つのドレンに向かう最長流路を短縮。分割して複数設置が基本。
• 端部からの距離:外壁や立上りから適正離隔(例:300〜500mm)を確保し、立上りの施工とメンテを容易に。
• 落ち葉・砂対策:ストレーナ(ごみ受け)+定期清掃。周辺が樹木豊富なら開口径大きめ・複数化で冗長性。
4-3. ドレン納まりの鉄則(改修・新築共通)
1. フランジの清掃・目荒し:油膜・ほこり・旧接着剤を確実に除去。
2. プライマー・溶着条件の厳守:温度・時間・圧着。試験片で溶着確認が理想。
3. 立上り〜ドレンの連続性:段差で水返しが切れないよう“面一”を意識。
4. 改修用ドレンの固定:コーキング頼みはNG。機械固定+止水材で多重化。
5. 緊急吐出の高さ設定:仕上レベルと内装しみ上がり高さを計算して、室外へ先出しの原則。
チェック:引渡し前に水張り試験(洪水試験)を計画。居住中は難しいケースも多いので、散水+レーザー水位で代替検証するなど、現場条件に合わせて“確からしさ”を積み上げます。⏱️
5. 立上り・端末・笠木の排水ディテール
• 立上り高さ:外部は原則200mm程度を目安(最低150mm)。サッシ下端が低い場合は水返し金物・溝型見切りで代替案。
• 笠木取り合い:ジョイント位置は水下に置かない。二重の水返しとシール二面接着で貫通止水。
• 出隅・入隅:コーナー部は補強メッシュや役物で応力集中を分散。
• 側溝(スリット):立上り際に浅い溝で線排水を作ると、面の滞水を減らせる。清掃性(幅・深さ)も設計要件。
6. 勾配・排水の“見える化”—計測と合否基準
• レーザーレベルで高低差を測定し、等高線図を簡易作成。改修前後を比較し逆勾配の撲滅を確認。
• 水たまり検査:散水停止60分後の滞水深さを記録。0〜数mmを目標、10mmを越える滞水は是正検討。
• ドレン流量:簡易的に満水→排水時間で流下能力を確認。ゴミ受け装着時の差も試す。
• 写真基準:広角→中景→寄り→ディテールの4点セットで誰が見ても分かる記録に。
7. 清掃計画も“設計”の一部
• 落ち葉期の前倒し清掃:秋だけでなく、春の花がら・虫の大量発生時期も詰まりやすい。
• 清掃動線:はしご・点検口・親綱アンカーの配置はメンテしやすい設計に直結。
• オーバーフロー点検:実際に水を流して外壁の汚れ・吐出位置・音を確認。クレーム予防に効果絶大。
8. 材料別の相性—ウレタン/シート/アスファルトの勾配観点
• ウレタン塗膜:平滑性が命。ピンホール対策に下地の気泡止め・プライマーの選定・通気緩衝工法+脱気筒で含水とガスを逃がす。
• シート防水:皺・ブリッジが勾配と相性悪化。曲率の大きい谷部は部分的に塗膜で納めるハイブリッドも選択肢。
• アスファルト:長寿命だが熱工法は火気・臭気対策が必須。大型屋上で計画的な勾配形成と相性良。
9. ケーススタディ:大型屋上の慢性的滞水を解消
状況:築25年RC造、屋上800㎡。既存は塩ビシート。中央機器基礎の背後に常時10〜15mm滞水。
診断:塔屋・基礎背面に谷地形。ドレン3基で流路が長い。オーバーフローは外壁の意匠上、吐出が外壁を汚してクレーム化。
対策: 1. テーパー断熱で“面の大勾配”を再構築(目標1/60)。 2. 基礎背面にクリケットを新設し、左右へ分流。 3. ドレンを3→5基に増設。各ドレン前にサドルを設置。 4. オーバーフローの吐出先を庇上に変更、縦樋で地上へ。
結果:散水停止60分後の滞水ゼロ。夏季表面温度が最大6℃低下し、材料負荷も軽減。清掃頻度は年2回→年1回へ。
10. 失敗あるあると未然防止 ⚠️
• ドレンだけ新品:周辺の逆勾配・谷がそのままで効果半減。→ 勾配形成とセットで設計。
• サッシ下端が低すぎ:立上り高さが取れずに水返し不足。→ 金物ディテール+部分段差で“見えない水返し”。
• 機器脚の“島”:四隅で水が回り込み滞水。→ 四辺の面取り+クリケットで水を逃がす。
• 清掃前提の過信:現実は清掃頻度が落ちる。→ 冗長化(複数ドレン)+大開口ストレーナで安全側へ。
11. 現場5分チェックリスト ✅
☐ レーザーで高低差測定→逆勾配地図の作成
☐ 目標勾配(1/50〜1/100)と勾配形成工法の確定
☐ サドル・クリケットの位置と寸法の合意
☐ ドレンの数量・位置・緊急吐出の高さ設定
☐ 立上り高さ(外部200mm目安)とサッシ干渉の解消案
☐ 材料別の納まり(ウレタン/シート/アスファルト)図
☐ 水張りor散水+レーザー水位で検証手順を事前共有
☐ 清掃・点検動線と安全設備(親綱・アンカー)の位置
12. まとめ—“走らせ・集め・落とす”を数値で証明
勾配は感覚ではなく数値と図で作る時代。レーザー・テーパー断熱・サドル/クリケット・改修用ドレンを組み合わせ、短い流路・冗長な出口・高い立上りで漏水リスクを根本から削る。最後は、滞水深・排水時間・写真で“水が動く建物”を証明しましょう。
次回予告:「第4回 下地補修(ひび割れ・爆裂・脆弱層の除去)」—防水は下地が命。爆裂の見極め、Uカット・樹脂注入、断面修復材の選定、可使時間・養生・打継ぎの勘所まで総ざらいします。
株式会社NSKでは一緒に働く仲間を募集しています♪
お問い合わせは↓をタップ♪
皆さんこんにちは!
株式会社NSK、更新担当の中西です。
調査のゴールは「原因の一次仮説を立て、再現性で検証し、是正案を図と数値で示す」こと。勘と経験だけに頼らず、段取りと記録で再現性を担保します。
1. 調査の原則と考え方
• 上流から下流へ:屋根→立上り→端末→面→ドレン→室内の順。先に室内だけ止めても本質的な解決にならない。
• 面・線・点の分解:面(床・屋根)/線(目地・取り合い)/点(ドレン・貫通)を分けて仮説化。
• 再現性:散水・採水・温湿計・含水計の値で“ビフォー/アフター”を比較し、因果関係を示す。
• 安全最優先:高所・感電・滑落・火気・居住者動線。調査そのものがリスクにならないように。
2. 事前ヒアリングと資料収集
• ヒアリング:いつから/どの雨(強風・台風・長雨)/どこに症状(天井・壁・サッシ)/季節性/時間差(雨後数時間)⏱️
• 資料:平立断の図面、過去の修繕履歴、保証書、赤外線・散水の過去結果、サーモ画像の原データ。
• 環境情報:建物方位、近隣高層の風影響、海岸・寒冷・多雪、屋上利用(歩行・荷重)。
コツ:居住者のスマホ写真・動画は宝の山。Exifの日時と天気(気象庁履歴)を突き合わせ、雨種(積乱雲のスコール/台風の横殴り)を同定します。
3. 調査計画(ITP:Inspection & Test Plan)
1. 仮説A:立上り折り返し不足+滞水 → 散水1:立上り→床→ドレンの順で15分区切り。
2. 仮説B:サッシ下端からの負圧吸引 → 散水2:風下想定でサッシ上部から順灌水。
3. 仮説C:ドレン鉛直継手のピンホール → 散水3:ドレン鉛直のみ局所散水+着色水。
• 計測・記録:温湿度、表面温、含水率、写真(広角→寄り)、動画(滴下・流路)。
• 合否基準:症状部での滴下再現/含水率上昇/サーモの温度差出現/散水停止後の遅延反応。✅
4. 目視・触診・打診(一次スクリーニング)
• 目視:ひび割れ(静的/動的)、ピンホール、チョーキング、膨れ、端末剥離、重ね代、溶着ビードの連続性。
• 触診:立上り端末の浮き、シールの硬化・三面接着、下地の柔らかさ(含水・腐朽の兆候)。
• 打診:中空音=脆弱下地/浮き。タイル・モルタル・押えコンクリートで有効。
記録テンプレ:A3図面に「赤=劣化、青=推定水みち、緑=調査済」を色分けし、通し番号(#001〜)で写真と連携。
5. 含水調査・計測機器の使い分け
• ピン式水分計:木部・石膏ボードなどの相対比較。仕上げを傷つける可能性。
• 非破壊式(電磁波):床・壁の相対的な分布把握に有効。膜厚や金属で誤差。
• コア抜き・採水:最終手段。位置と復旧の合意を事前に。
• 温湿度・風速:散水時の条件ログ。台風時の再現は難しいが、負圧箱や送風で傾向を作れる場合あり。
6. 赤外線サーモグラフィの使いどころ
• 原理:含水部は蒸発冷却・熱容量差で温度分布が変わる。朝夕の温度勾配が出る時間帯が最適。
• 撮影条件:
o 直射日光の反射を避ける(早朝/夕方)。
o 風速が低い日(風で表面温が均される)。
o エミッタンス:塩ビ・ゴム・ウレタン・FRPで0.90〜0.95を目安に設定。※機種により名称差あり。
o 温度差(ΔT)5℃以上が望ましい。
• 誤判定あるある:
o 塗り重ね差・色差→温度差に見える。
o 直射で温められた笠木・金物の反射。
o 風下面の“陰”が冷たく映る。
• 判定のコツ:サーモだけで断定しない。含水計・散水の反応と突き合わせ、水みちの連続性で見る。
7. 散水試験の組み立て(再現性が命)
• 準備:
o 養生(室内・電気設備・配線)。
o 2人以上の体制(散水担当/記録担当)。
o タイマー・無線・着色剤(食紅系)・紙テープ(散水範囲マーキング)。
• 順序:
1. 最上流(立上り・笠木)から15分。
2. 取り合い(サッシ・目地)15分。
3. 面(床)→ドレン周り15〜30分。
• ポイント:
o 一度に広く濡らさない(原因特定が曖昧に)。
o 反応が出たら即停止し、範囲を絞って再現。
o 雨後の遅延(数十分〜数時間)を観察。⏳
• 記録:
o 写真は「散水範囲→散水中→反応→停止後」の4枚を1セット。
o 室内は吸水紙や「キッチンペーパー+透明テープ」で滴下形状を残す。
8. 補助手法(トレーサー・発煙・エンドスコープ)
• 蛍光トレーサー:紫外線ライトで流路を追う。ドレン系統や埋設配管で有効。
• 発煙:室内側から加圧し外部へ漏れを視認(火気厳禁・換気必須)。
• エンドスコープ:笠木内・配管チャンバーの内部確認。復旧性の高い穴位置を選定。
9. レポート作成—“誰が見ても同じ結論”へ
• 構成:
1. 表紙(物件概要・調査日・天気・温湿度)
2. サマリー(結論・推奨工法・工期・概算)
3. 調査方法(機器・設定・散水手順)
4. 事実(写真・数値・図面に連番で)
5. 考察(面/線/点の因果)
6. 是正案(納まり図・仕様・検査基準)
• 写真:1枚1キャプション。主語・動詞で「何がどうなった」を明確に。
• 図:水みち矢印/想定上流・下流。検討の跡が残る図は説得力が段違い。
10. 安全・近隣対応
• 高所・転落・滑落の対策(親綱・ハーネス・立入禁止)。
• 散水による飛散が近隣・歩行者に及ばない導線計画。
• 室内側の養生・停電対応・避難経路確保。
• 居住中調査では掲示・ポスティング・声かけをセットで。
11. ケーススタディ:外壁取り合い×台風時のみの漏水
• 症状:南面の掃き出しサッシ下で台風時のみ。通常雨では無症状。
• 仮説:負圧吸引+サッシ下レールの毛細管攀登。立上り端末の折返し不足も疑い。
• 調査:
o 夕方のサーモでサッシ下に線状の低温帯。
o 散水(上部から)では再現せず、横吹き散水で10分後に室内側へ滴下。
o 含水は立上り端末〜下端の連続性。
• 是正:サッシ下端の水返し金物新設、立上り200mmの再防水、サッシ両端の二面接着。再現なしで完治。
12. 使えるチェックリスト(現場5分)✅
☐ 図面・過去修繕・保証の回収
☐ 屋上・バルコニーの勾配と滞水の確認
☐ 立上り折返し高さ(150〜200mm)
☐ 端末金物・改修ドレン・脱気筒の有無
☐ サッシ周りのシール:二面接着/バックアップ材
☐ 散水の順序計画(上流→下流、15分刻み)
☐ サーモの撮影時間帯(朝夕)と設定メモ
☐ 含水計・温湿度・風速のログ準備
☐ 記録フォーマット(連番写真、A3マップ)
13. よくある失敗と回避策 ⚠️
• いきなり全面散水:原因の切り分け不能に。→ 狭域・順序・時間を守る。
• サーモ画像の“色”で判断:温度スケール未設定で誤読。→ 数値・ΔTを注記。
• 居住者への告知不足:苦情・中断・やり直し。→ 掲示+ポスティング+当日声掛け。
• 復旧性を考えない穿孔:信頼失墜。→ 位置合意と復旧計画を先に。
14. まとめ—診断は“仮説→検証→記録”の学術プロセス
防水診断の価値は、原因の同定精度と、是正案の実効性にあります。目視・含水・赤外線・散水を順序立てて組み合わせ、再現性で妥当性を証明する。最後は図と数値で意思決定者が迷わない資料に仕上げること。これが、雨漏りゼロへの最短経路です。
次回予告:「第3回 勾配・排水計画とドレン納まり」—滞水1mmが寿命を縮める? 勾配形成(モルタル・断熱下地・セルフレベリング)と改修用ドレン・縦樋接続・脱気の要点を、図解イメージで整理します。
株式会社NSKでは一緒に働く仲間を募集しています♪
お問い合わせは↓をタップ♪
皆さんこんにちは!
株式会社NSK、更新担当の中西です。
「雨漏り」は“現象”であって“原因”は一つではありません。素材・納まり・経年・使用環境が連鎖して起こる“合成リスク”です。本編では、どこから水が入り、どう留め、どう管理するかを“現場で役立つ順番”で解説します。
1. 防水の役割—構造を濡らさないという設計思想
建物の耐久性は「構造体を濡らさない」ことに尽きます。鉄筋コンクリートは中性化を早め、鉄骨は腐食、木造は腐朽菌・シロアリのリスクが高まります。防水は一次防水(仕上げ)と二次防水(下地・防水層)の二重で考えると理解が早いです。屋根・屋上・バルコニー・開放廊下・浴室のような“常時濡れる場所”は、二次防水(主防水)が主役、サッシ・外壁のような“雨仕舞い中心の場所”は一次防水(仕上げ+板金)を確実にしつつ、二次防水でバックアップする設計が基本です。
2. 雨水が入る“道”を知る—面・線・点 の3分類
雨水の侵入は大きく以下の3つに分解できます。 – 面(面状):屋上スラブやバルコニー床など、面全体からの浸透。微細なクラックや防水層の劣化、膜厚不足で起こります。 – 線(線状):シーリング目地、立上りと床の取り合い、笠木ジョイントなどの“線”。動き(伸縮・温度差・風荷重)に追随できず、微開で漏水。 – 点(点状):ドレン、配管貫通部、ビス穴、釘孔、手すり支持金物など。小さな穴1つで大量に入ります。
✅ 現場メモ:調査は「面→線→点」の順で広い方から狭い方へ。散水試験も上流→下流の順。先に“点”だけ塞ぐと、別経路の再現性が消えて原因特定を誤ります。
3. 物理現象を押さえる—負圧・毛細管現象・水の滞留
• 負圧吸引:台風時、風で外壁表面が負圧になり、風下側の隙間から室内方向へ水が吸い込まれます。見た目「逆流」に注意。
• 毛細管現象:0.1〜0.3mmの微細な隙間でも水は横移動します。仕上げの重なり向き・端末の折返し・差し込み寸法が重要。
• 滞留:勾配不足で水が溜まると、紫外線+熱で防水層が劣化加速。藻・埃堆積→微細なピンホール→雨量ピークで漏れる、の流れに。
4. 防水工法の全体像—“正解”は一つじゃない
代表的な工法の性質を改修目線で対比します。 – ウレタン塗膜防水(密着/通気緩衝):複雑ディテールに強い。連続被膜で継ぎ目が少ない。含水下地は通気緩衝で逃がす。膜厚管理が命。 – FRP防水:軽量・硬質、ベランダで定番。立上りの折返しが取りやすい。下地動きにやや弱いのでジョイント処理に配慮。 – シート防水(塩ビ・ゴム・TPO):工場製の品質が担保される。溶着・機械的固定で施工スピード◎。複雑形状は納まり検討を厚めに。 – アスファルト防水:信頼性が高く長寿命。熱工法は管理と安全対策が必須。大型屋上や長期保全計画で有力。⬛
選定の軸:①下地の含水・動き②ディテールの複雑さ③既存防水の種類④改修時の騒音・臭気制限⑤歩行・荷重 ⑥予算と保全計画。
5. 現場フロー—“段取り八分”の型
1. 事前調査:図面・改修履歴・保証書・漏水履歴を収集。含水率・打診・赤外線・散水の順で仮説を立てる。
2. 仮設・安全:転落・開口・火気・動線分離。住戸・テナントへの告知。養生計画は“水の流れ”も想定。
3. 下地補修:爆裂・脆弱部除去/クラック注入/不陸調整/勾配形成。仕上げの前に水がたまらない形を作る。
4. プライマー:素材・含水率・温湿度で選択。可使時間・塗布量を守る。養生期間は焦らない。
5. 主防水:工法に応じて膜厚・重ね幅・溶着条件を数値で管理。小口の端末と立上りに時間を配分。
6. 端末・役物:ドレン、改修用ドレン、脱気筒、笠木取合い。“出口”の確実性=長寿命。
7. 検査・記録:中間検査→是正→最終検査。写真・膜厚計・溶着試験片・含水ログを残す。
8. 引渡し・保証:使用上の注意、清掃・点検周期、保証範囲。アフター点検の期日を契約書に明記。
6. よくある誤解—“塗れば止まる”は危険 ⚠️
• 原因不明のまま全面塗り:再発時に原因追跡が困難。調査費用の“節約”が、後の手戻りコストを増大させます。
• ドレン未改修:既存ドレンの不良を放置して表面だけ更新。漏水は“面”よりも“点”からが多い。
• 立上りの折返し不足:最低でも規定高さ(一般に150mm目安、外部は200mm推奨ケースも)を確保。掃き出しサッシ下端が低い場合は特別納まりを設計。
• 乾燥不十分:含水を閉じ込めると膨れ・剥離。通気緩衝・脱気筒・天候待ちの判断がプロの差。
7. チェックリスト—着手前5分で安全・品質UP ✅
☐ 図面・改修履歴・漏水マップの入手/共有
☐ 勾配・滞水箇所・ドレン機能の確認
☐ 含水率・温湿度の計測と記録
☐ 仮設転落防止・立入禁止・火気許可の整備
☐ 下地補修範囲の合意(写真+数量)
☐ 端末・立上り・役物の納まり図承認
☐ 膜厚・溶着・重ね幅等の検査基準設定
☐ 中間・完了検査のスケジュール化(関係者同席)
8. ケーススタディ—ベランダ“点漏水”を止める
症状:大雨と強風時のみ、窓際の天井にシミ。通常雨では無症状。
仮説:サッシ周りの線状・点状の複合。風圧でサッシ下端から吸引→バルコニー床の勾配不足で滞水→ドレン周りの防水端末が弱点。
対策: 1. サッシ両端の目地を撤去・再シール(二面接着・背面材管理)。 2. バルコニー床は通気緩衝ウレタンで再防水、立上り200mm確保。 3. 既存ドレンに改修用ドレンを挿入+フランジ溶着。脱気筒を新設。結果:散水再現なし。台風時も無事。原因は“点”+“滞留”の相乗でした。
9. コスト・耐用年数・ライフサイクル
• 耐用年数は“材料寿命×使用環境×メンテ”の掛け算。直射日光・滞水・歩行荷重・塩害・寒冷地は劣化促進。
• 見積比較は単価だけでなく、下地補修・端末金物・改修ドレン・脱気・検査記録・保証条件まで総額で。
• 提案の良し悪しは“ディテール図の有無”と“検査の数値化”。図と数値が弱い見積は、再発リスクを価格に転嫁していない可能性。
10. FAQ よくある質問 ♀️
Q1. 雨漏り箇所の真上を直せば止まりますか?
A. いいえ。水は“上流”から回り込みます。調査は広く、対策は上流から。
Q2. 梅雨時は施工できますか?
A. 可能な工法もありますが、乾燥・養生時間を厳守。通気緩衝×脱気でリスク低減。天候リードタイムを計画に組み込みましょう。⛅
Q3. どの工法が一番長持ち?
A. 条件次第。大型屋上ならシート・アスファルト、複雑なベランダならウレタンが有利など、“適材適所”が最長寿命の近道。
11. まとめ—防水は“水のデザイン”
目に見える仕上げよりも、水の入り方・流れ方・出し方をデザインするのが防水です。原因を面・線・点で分解し、上流から順に潰す。勾配とドレンを整え、端末・立上りを丁寧に。数値で検査し、記録を残す。これが“雨漏りゼロ設計”の基本形です。
次回予告(概略):「下地調査と雨漏り診断」—赤外線は“万能の証拠”ではありません。目視→打診→含水→赤外線→散水の順で仮説検証。散水は上流から、写真と計測値で“再現性”を記録します。
________________________________________
お問い合わせ・ご相談 ✉️
「自宅や物件で雨漏りが不安」「見積を比較したい」「図面上で納まりを検討したい」など、お気軽にご相談ください。現場で使えるチェックリストやディテール図のひな形もご用意できます。✨
株式会社NSKでは一緒に働く仲間を募集しています♪
お問い合わせは↓をタップ♪
皆さんこんにちは!
株式会社NSK、更新担当の中西です。
さて今回は
~点検・メンテの“黄金サイクル”~
防水は施工して終わりではありません。トップコート・シーリング・ドレン清掃などの軽メンテを回すだけで、寿命は大きく伸びます。今日は、年間点検の型と台風・豪雨時の応急処置をまとめてご紹介。管理者・オーナー必見の実用編です。📒🔧
目次
春(黄砂・花粉後):表面汚れの洗浄→トップコート摩耗の目視
梅雨前:ドレン清掃・落ち葉除去・脱気筒の詰まり確認
台風前:笠木・手すり根元・シーリングの痩せ・割れチェック
冬入り:ひび割れ・浮き・凍害の予兆確認/記録更新
ルール化📌:“梅雨前・台風前”は必ず屋上に上がる。 これだけでトラブル激減。
ドレン:枯葉・砂で詰まり→必ず清掃
立上り端部:捲れ・シワ・割れがないか
笠木・ジョイント:シーリング亀裂/コーキングの痩せ
表面摩耗:色抜け・チョーキング→トップコート更新サイン
ふくれ・浮き:踏むと柔らかい→含水の可能性
ひび割れ:下地クラック→幅・長さを記録
勾配不良・水溜まり:チョークで位置マーキング
トップコート:3〜5年ごと更新
シーリング:5〜7年ごと打ち替え(環境で前後)
防水本体改修:10〜15年を目安(下地状態次第)
迷ったら劣化写真+面積+既存仕様を揃えて専門家に相談を。📷📝
定点撮影:ドレン/立上り/端部/笠木を毎回同じ角度で
ファイル名:「年月日_場所_劣化種別」
簡易図面に番号を振り、写真と対応させると後で効く
室内二次被害の抑制:漏水点の下に養生・受けバケツ、電気系統はブレーカー確認
外部の一次止水:防水テープ・シーリングは乾いた面に。雨中の作業は安全最優先
ブルーシートは最終手段:風対策・端末処理が甘いと逆効果に⚠️
原因特定は後日:晴天時に試験散水で再現→恒久対策へ
設備基礎まわり:室外機・アンテナ脚の根元シール切れ
後施工アンカー:穴周りの止水不足→シーリング+キャップ
内樋ルート:配管劣化・継手ゆるみ→改修ドレン検討
現場情報:面積、既存仕様、劣化写真、アクセス(搬入経路)
希望仕様:歩行耐久・メンテ性・工期・騒音配慮の優先度
範囲の線引き:下地補修・シーリング・端末金物・改修ドレンの含む/含まないを明記
保証対象:防水本体のみ? 端末やシーリングは?
定期点検条件:トップコート更新や清掃の実施記録
写真・工程記録:着工前→中間→完了の三段階で保管
“施工後の運用”こそが防水寿命を伸ばす最大のカギ。定期点検+軽メンテ+記録の三点を回せば、雨漏りは「起きてから対処」から**「起きない運用」**へ。点検メニューの作成や年間保守も承っています。お気軽にご相談ください。🛠️📞
株式会社NSKでは一緒に働く仲間を募集しています♪
お問い合わせは↓をタップ♪
皆さんこんにちは!
株式会社NSK、更新担当の中西です。
さて今回は
~“正しい選び方”~
「どの防水がうちに合うの?」—屋上・バルコニー・ルーフバルコニーなど、場所と使い方で最適解は変わります。本記事は代表的な4工法の特徴から、見積書の見方・失敗しないポイントまでを一気に解説。初めての方も、改修検討中の方も、これさえ読めば方向性が決まります。✨
目次
歩行頻度が高い(屋上庭園・バルコニー) → FRP or 塩ビシート(歩行用仕様)
複雑な形状・ドレンが多い → ウレタン塗膜(通気緩衝)
広い面積・メンテ容易性重視 → 塩ビシート機械固定
重防食・長期耐久を最優先 → アスファルト(改質アスファルト)
迷ったら:下地状態と納まりで決めるのが正解。構造体・既存防水・雨仕舞を現調で見極めます。
露出仕上げ:防水層が表に出る。定期トップコートで保護。
保護仕上げ:タイル・モルタル・砂利等で防水層を覆い耐久性UP。
密着工法 / 通気緩衝工法:下地に含水がある改修は“通気緩衝+脱気筒”が鉄板。
特長:液体を塗って連続皮膜を形成。複雑納まり◎
向き:改修全般、入隅・出隅が多い形状
強み:継ぎ目が無く“止水補修”も相性良し
注意:天候依存・乾燥時間が必要/厚み管理が命
特長:硬質で耐摩耗・耐衝撃に強い。歩行多用◎
向き:戸建バルコニー、ルーフバルコニー
強み:工期短め/納まりシャープ
注意:下地の動きに弱い→下地設計と伸縮目地が鍵
特長:工場製シートを貼る。品質の均一性が魅力
向き:広面積屋上、改修、機械固定で既存の上に施工可
強み:耐候性・メンテ容易/継手は熱溶着で確実
注意:立上り・端末金物の設計が品質を左右
特長:重ね貼りで層を積む重防水。長期耐久
向き:新築大屋根、重歩行・長寿命志向
強み:歴史的実績・耐久性
注意:重量・熱工法の計画が必要/改修は要工程
立上り:最低H=250mm目安、笠木との取り合いを確実に
ドレン:改修ドレンで既存管の中へ差し込み、漏水リスクを根本対策
端末金物:パラペット天端・見切りの押さえ金物+シーリングで仕上げ
層構成・仕様書の有無(プライマー/主材/トップ)
通気緩衝・脱気筒の数量(改修時)
端末金物・改修ドレン・シーリングの範囲
下地補修(ひび割れ、浮き、勾配調整)
仮設(足場・養生・搬入出・廃材処理)
平米単価だけで判断NG。**“何をどこまでやるか”**がコストの本質です。
降雨・結露・露点を確認して施工可否を判断
低温期は硬化遅延、高温期は可使時間短縮に注意
試験散水や赤外線カメラ(必要に応じ)で完了検査
膨れ:含水下地→通気緩衝+脱気で予防
端末の剥離:金物固定不足→ピッチ管理と下地補強
再漏水:原因未特定のまま再施工→事前に漏水調査!
防水は“材料の優劣”ではなく、下地・納まり・工程の総合設計が勝負。現地調査で最適解を見つけ、仕様書ベースで施工すれば、長く安心が続きます。まずは無料現地診断からどうぞ。️
株式会社NSKでは一緒に働く仲間を募集しています♪
お問い合わせは↓をタップ♪
皆さんこんにちは!
株式会社NSK、更新担当の中西です。
さて今回は
~経済的役割~
ということで、建設業界において、「防水工事」はしばしば目立たない存在とされがちですが、実はその経済的意義は非常に大きく、多方面に波及しています。防水工事が果たす役割を見直すことで、建設全体の生産性向上や建物資産の価値維持、地域経済への貢献といった多くの経済効果が浮かび上がります。
目次
防水工事は、屋上や外壁、バルコニー、浴室など、建物の各部位に水の侵入を防ぐ処理を施す工程です。この工程がしっかりしていないと、建物内部に水が入り込み、劣化、カビ、構造体の腐食といった深刻な問題を引き起こします。
このような問題は、後々の修繕や入居者トラブルに直結し、経済的損失につながるため、初期段階での質の高い防水工事は、いわば「予防投資」としての経済価値を持ちます。
建物の資産価値は、外観や設備だけでなく、「劣化のしにくさ」によって大きく左右されます。特にマンションや商業施設においては、漏水が発生した時点で資産価値が急落することもあり、防水工事はその防波堤としての役割を担っています。
防水層の寿命が長くなれば、修繕周期が延び、ライフサイクルコスト(LCC)の低減が可能になります。これにより建物オーナーの経済負担を減らし、建物経営の健全性を高めることができます。
防水工事業者の多くは地域密着型の中小企業であり、地域の雇用創出に貢献しています。工事の発注があれば、職人、資材商社、運送業者、設計士など様々な業種に経済活動が広がります。
さらに、公共施設や学校の防水改修工事などでは、地元企業への発注を通じて地域経済の循環にも寄与しています。
例えば、数十億円規模のマンション開発において、防水工事は全体コストの数%にすぎません。しかし、これを怠ることで漏水事故が発生した場合、補修費や訴訟リスク、ブランド価値の低下など、何倍もの損失が生じる可能性があります。
つまり、防水工事は「リスク管理の経済的手段」であり、コスト以上のリターンをもたらす投資と位置づけられます。
環境意識の高まりと共に、防水工事にも環境配慮型材料や長寿命化技術の導入が進んでいます。これにより、廃棄物の削減・再施工の頻度減少・省資源化が実現し、サステナブルな建築の基礎を築いています。
この動きは、環境ビジネスとしての建設業の評価を高め、新たな市場機会と経済効果を生み出しています。
防水工事は「目に見えにくい投資」であるがゆえに、その経済的価値が過小評価されがちです。しかし、実際には建物の寿命、修繕コスト、資産価値、地域経済、安全保障まで、多方面で大きな役割を果たしています。今後は、より高度な防水技術と経済戦略が融合し、建設業における価値の源泉となっていくでしょう。
株式会社NSKでは一緒に働く仲間を募集しています♪
お問い合わせは↓をタップ♪
皆さんこんにちは!
株式会社NSK、更新担当の中西です。
さて今回は
~多様化~
ということで、防水工事における多様化の実態と、それが建設業界にもたらす影響について掘り下げます。
建物の寿命や快適性に大きく関わる「防水工事」は、建設現場における最後の砦とも言える重要な工程です。かつては一部の熟練職人の技術に頼る世界でしたが、現代ではその在り方が大きく変化し、多様化が進んでいます。
目次
防水工事とは、建物内部に水が侵入するのを防ぐために、防水層を施工する作業です。屋上・バルコニー・地下室・外壁・浴室などが対象となり、雨漏り・劣化・カビの発生を防ぎ、建物の資産価値を守ります。
従来はアスファルト防水やシート防水が主流でしたが、現在ではウレタン塗膜防水、FRP防水、高反射防水、無機系防水材など、建物の用途や構造に応じて多様な工法が使い分けられています。
この多様化により、耐久性や施工期間、コスト、環境性能に応じた最適な提案が可能になりました。
近年では、VOC(揮発性有機化合物)を含まない水性防水材や、太陽光の反射率が高くヒートアイランド対策になる「高反射防水」など、環境負荷の少ない素材へのニーズも高まっています。
従来の肉体労働中心の現場から、作業環境や道具の改善が進んだことで、女性や外国人労働者の参入も増えています。特にウレタン塗膜防水やシート貼り作業などでは、繊細な作業が求められるため、女性職人が重宝される場面も。
高齢の熟練者が教育者・管理者として若手を指導する流れも強まっており、技能継承と安全意識の共有が重要なテーマとなっています。
新築住宅からマンション改修、商業施設、公共施設、さらには工場や物流倉庫など、案件の規模・種類が多様化しています。これにより、工法選定や施工スケジュール、品質管理の方法も個別に対応する必要が出てきました。
一度の工事で何十年も耐久性を持たせたいというニーズが高まり、点検・保守との連動や、施工保証付きのプランなども増加しています。
防水工事の分野でも、ドローンを用いた屋上調査、施工写真のクラウド管理、AIによる劣化判定、施工進捗の可視化アプリなど、ICTの導入が進んでいます。こうした技術により、提案力・説得力・作業効率の向上が実現しています。
防水工事は今後ますます「提案型ビジネス」へと変化していくでしょう。現場での技能だけでなく、顧客との対話、設計段階からの関与、アフターケア体制の充実など、多面的な力が求められる時代が始まっています。
株式会社NSKでは一緒に働く仲間を募集しています♪
お問い合わせは↓をタップ♪